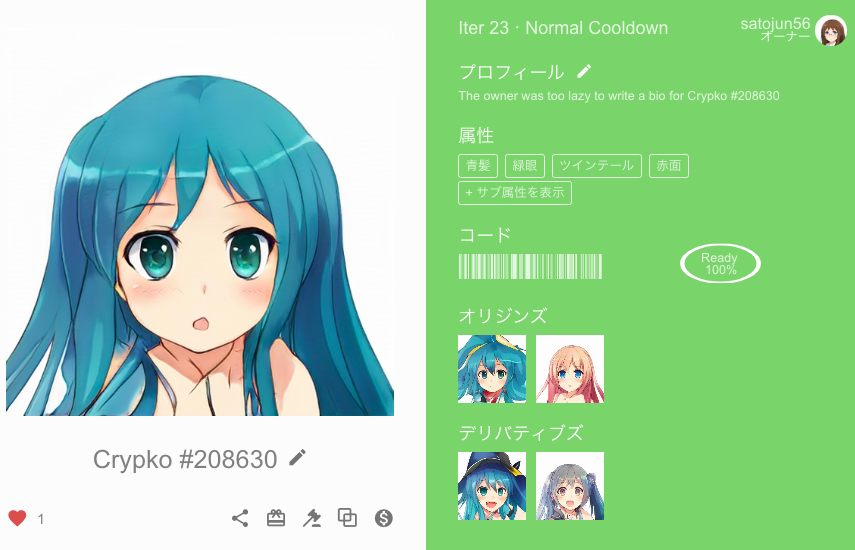こんにちは。
今回ご紹介しますのは、8代目林屋正蔵(彦六)師匠です。
弟子の林家木久扇師匠による
「馬ぁ鹿野郎ぉ、はやく食わねぇからだァ」
というモノマネだけは聞いたことがある、という方も多いかもしれませんが、実際に正蔵師匠の落語を聞いてみると驚くべきことに、あのまんまです。
はじめのうちは「もっと速く喋れないのか?」とイライラさせられますが、これに慣れてくると、独特の、たまらない味わいのある噺家さんです。
今回はそのへんの味わい方も含めて、正蔵師匠の魅力をご紹介します。
林屋正蔵の、スゴいところ
空気感がスゴい
正蔵師匠がしゃべり始めると場の空気がガラッと変わります。
大抵の噺家さんは、まずはマクラで世間話や時事ネタをしゃべり、スルリと演目に入っていく、その変わり目が自然でさり気ないほど、上手だ、粋だということになるわけですが、、、
正蔵師匠の場合はもう、イキナリです。
そもそもマクラらしいマクラもたいして言わない、せいぜいが予備知識の説明くらいです。
芝居噺や怪談話が得意という要因もあるんでしょうが、高座に上がって最初の一語を発した瞬間、もうそこには既に江戸の空気が立ち込めています。
正蔵師匠の語り口には、「語り部」とでも呼ぶのが似合う、独特のニュアンスがあります。
志ん朝師匠なんかが醸し出す、市井の「江戸っ子」の空気ともちょっと違いますね。
もっとワザとらしいというか、「今から、おもしろい作り話を語りますよ」とでも言うような、芝居がかったニュアンス。
で、その空気感がすこぶる濃い。
これが良いことなのかというと、まあ悪い面もあって(笑)、
場合によってはどうにもワザとらしくて笑うに笑えないなんて時もあるんですが、でも、「この感じ」でなくてはサマにならない演目というのもやはり存在します。
あとで紹介する「やんま久次」「生きている小平次」をはじめとして、正蔵師匠以外にはあまり演じ手のいない「からっ風侍」「めだか」なんていった演目は、正蔵師匠でなくてはアジが出せない噺だと思います。
笑えないところがスゴイ
こう言っちゃうと「何だそれは」と思われるかもしれません。
でも、「笑えるから落語」って訳でもないんですよ。志ん生師匠なんかは、落語というのは「オツなもの」だと言っています。
まあ志ん生師匠は普通に笑える噺家ですけど。私はこの「オツさ」を極めた噺家こそが、正蔵師匠だと思っています。
ちょっと説明させていただくと、オツというのは「甲・乙・丙」の乙のこと。二番目。
最高、ではないんだけど、これはこれで味があって面白いよね。むしろ万人受けする一番じゃない、ちょっと捻ったところがあるのが洒落ているよね。っていう感覚。寿司で言えばコハダっていうやつです。
正蔵師匠はこの「オツ」を、強烈に感じさせてくれる噺家です。
ドッカンドッカン爆笑を取るようなタイプではなく、たまにギャグもやるけどベタベタ過ぎて笑えたもんじゃない。だいいち話すスピードが遅すぎて、しゃべってる途中でオチが見えちゃう。
それなのに、不思議と、なーんかイイんですよ。聴いてると気持ちいいんです。
格好いい、洒落てる、粋、そんな感覚がなんとなく浮かぶのですが、それがまた決してスッとは心に入ってこない。必ずぎこちなくヒネった形で胸に刺さってくる。
コハダ、どじょう鍋、木の芽田楽・・・ そんな「オツ」に通じる味わいを持った噺家です。
スローさがスゴい
ご存知のように正蔵師匠の話し方は、スローで、ヘロヘロです。なんだかこの人だけ、時間の流れ方が違うんじゃないかってくらいゆっくりです。
まあ年寄りってのはえてして動作が遅いものではありますが、しかし巷に溢れるノロい年寄りと、正蔵師匠には決定的な違いがあります。
それは、自身のゆっくりな流れに、聴衆を引き込んでしまうパワーです。
なんというか、一言ひとことに重みと深みがあって、聴き手をガッチリと捕まえて話さないのです。我々聴き手のペースは正蔵師匠の話すスピードよりもはるかに速いはずなのに(笑)、先へ先へと急ぐことを許さない「いいからお前ェ、せかせかするんじゃ無ぇ。しゃんとしろォ」とでも言うかのような、有無を言わさない言葉の重みで首根っこを捕まえられ、強制的に正蔵師匠のペースで歩くことを強いられる、そんなパワーがあるんです。
で、それが不快なのかというともちろんそうではなく、あえてテンポを落とすことによって初めて生まれる、独特の味わいがあるのです。
沼の上には、白い、藻の花が咲いておりまして、
覆いかぶさるよゥにィ、暗いィ木立を写して、
どんよりと、淀んでおりますゥ水のおもて。
空は、露を含んでおりますか、暗いのですが、
遠いィ山々の、端のほうにィ、青空がちょいと見えまして、
そこから、
わびしいィ光の矢がひとすじ、この古沼を、差しております。
「生きている小平次」からの一節。
こういった情景描写は話の本筋とは関係ないので、ともすれば聞き流しがちです。しかし正蔵師匠の噺だと、不思議とじっくり聞き込んじゃうんですねぇ。
ひとつひとつ、丁寧に思い浮かべながら聞いてみると、実にワビサビの効いた、雰囲気ある情景です。
林屋正蔵の、おすすめ演目
やんま久次
旗本の次男坊の久次郎は、働きもせずに兄に金をせびっては遊んでいる道楽者。今日も兄のところに金をゆすり取りに行きますが、いいかげん腹に据えかねた兄と、これを見かねた剣術の師匠。こんなやくざ者がいたのでは家名に傷がつくからと、久次郎に切腹を迫ります。
必死の命乞いでなんとか許してもらった久次郎。これからは心を入れ替えて、侍奉公をすると師匠に誓います。去って行く師匠の背中に向けて、久次郎はこんなことを言います。
馬鹿より怖ぇ者は無えってなァこれだよ。エェ?
人斬り包丁を振り回しゃがって。
ビックリさせやがるじゃねえか。エェ?
オイ、てめえに剣術を教わったってな、
ただ教わったんじゃねえぞ。
月々のものは持参をして、たまにゃ中元に、タクアンの五、六本も持してやる。
てめぇ何て言いやがった?
先だって頂戴した沢庵は、美味しゅうございましたって、
エェ? タクアンの目利きをしやがって。
オゥ、お前っちの道楽と言やぁ、
金魚を生やかしやがったり、朝顔にどぶ泥を引っかけたり、
三道楽煩悩のどれひとつ、手前は楽しんだことはあるめぇよ。エェ?
俺の屋敷に俺が行くのに、他人のてめえの差配には及ばねぇや!
大べらぼうめェ!
この「やんま久次」という演目じたい、風変わりな演目といいますか、変な噺なんですよね。
大筋としてはプー太郎の次男坊が、おっかない先生に脅かされて心を入れ替えるが、実はそれは上っ面だけで、最後に悪態をついて終わりという、なんてことはない話です。
たいして意外性も面白味もない話なんですよね。
じゃあ聞きどころはドコなのかというと、やはりラストの「大べらぼうめぇ!」のキメっぷりしかありません。
ココの「名調子」を味わうのが、この演目の醍醐味です。
そこへ持ってきて、正蔵師匠ですよ。
これがスゲエんです。
やっぱりあの調子なんだけど、でも凄みがあって、重みがあって、格好いいんです。
理屈では説明できない何かが起こっています。
こんなヘロヘロとしたカタルシスは、世の中どこを探しても、ココにしかありませんよ。
威勢のいい啖呵といえば志ん朝や談志が思い浮かびますが、
ではこの「大べらぼうめ!」を、志ん朝や談志が言ったとしたらどうでしょう?
想像してみてください。なんか上滑りしそうな気がしませんか?
生きている小平次
奥州郡山の安積沼。船を浮かべて釣りをする二人。役者の小幡小平次と、太鼓打ちの那古太九郎。幼馴染の二人ですが、今日は小平次から折り入って相談があるということ。
聞けば、小平次はかねてから太九郎の妻のおちかに想いを寄せていて、譲ってくれと言う。話はまとまらず、喧嘩になった二人。太九郎はカッとなって小平次を殺してしまいます。
やがて、江戸で夫の帰りを待つおちかの元に現れたのは、なんと小平次でした。
「太九郎は自分が殺してしまった。一緒に逃げてくれ」という小平次。しかしそこに帰ってきた太九郎。ふたたび脇差しで小平次を刺し殺します。
役人の手を逃れるため、おちかと太九郎は江戸を離れます。しかし太九郎は、旅の途中の宿屋で、ふたたび小平次を見たと言います。
まるで、何者にか糸で引かれるように、
太九郎はこの場を立ち去ってしまう。
おちかも後を追っていく。
いままで、ふたぁりが休んでいた真っ暗がりの奥の方から、
ポツリと、明かりがひとつ見えまして、
やがて近づいてくると、提灯を下げた旅姿の、
額から、顎へかけてひとすじのきずのあるたびびとが、
おちか太九郎のあとを追うように、
とぼとぼと、此処を過ぎ去ってしまうやがて、
提灯の明かりも失せ、真っっ暗がりの闇の中。
聞こえるものは、風の音。
波の音。
これがラストの場面。
正蔵師匠の小平次は、なんとも言えない哀愁がありますね。
「うらめしや」なんて野暮なことは言いません。
おちかの前に現れた時には、ただひたすらに自分の想いを告げ、一緒に来てくれと頼むだけ。それであっけなく再び斬り殺されます。
江戸を去ったおちか太九郎を追いかけても、しょんぼり宿屋の脇に立っていたり、トボトボと後ろを歩いてみたり。
「幽霊になってしまうまでの事情」に同情できる幽霊は多いですが、
「幽霊になってからの振る舞い」にまで同情できて、親近感の湧く幽霊というのはかなり珍しいと思います。
で、スゴイのは最後の
「風の音、波の音。」です。
三者三様のせつない心境が簡素な情景へと回収されていく、儚く、さわやかで、余韻豊かな、非常に格調高い締めくくり方です。
このラストはまさに、名人芸と言って差し支えないでしょう。
二つ面
「生きている小平次」の後日談というか、数世代後を描いた噺です。
文明開化の明治の世。
柳亭西柳は怪談噺を得意とする噺家ですが、近頃のお客さんは「幽霊」なんてものを信じなくなってしまって、怪談をやっても笑われてしまう。
そんなある日、西柳の前に現れたのが、彼が常々演じている小幡小平次の幽霊その人。小平次の幽霊が言うには、師匠がいつも付けている面の他にもう一つ、後ろにも面をつけなさい。笑う客には二つ面を見せること。無いはずのところに面があるので、客はぎょっとするでしょう、と。
「師匠、寄席の帰りだからお前さん、小腹が減ってるだろう何か奢ろう。
ネ、ご馳走しよう。何がいい?」
「左様でございますかコレぁどうも・・・
申し訳がございませんでアタクシは、
温かい物でも・・・」
「蕎麦?」
「イエイエイエ・・・お蕎麦よりか、
お寿司が頂戴したいんで・・・」
「寿司ィ?
ヘェー・・・話せるねェ。寿司。ふぅーん。
寿司は何が好きだい?」
「アタクシはもう、人間が下品なせいか、
コハダ・・・
・・・コハダ様がいちばん・・・」
「何だいンなとこぃ様ァ付けなくったって良いよ。
コハダが好き?
あっしも好きなんだ共食いだ」
小平次が西柳と近づきの印に一緒に寿司でもということで、ゴキゲンでコハダの寿司をパクつきます。
シリアスな「生きている小平次」とは打って変わって、幽霊は登場するものの、終始ほのぼのとしています。新春の晴ればれとした空気感を感じさせる、ハートフルな演目です。
さて小平次の幽霊が醸し出すコミカルさと対になり、この物語のもうひとつの軸を成すのが、西柳師匠と弟子の佐太郎の関係です。
「佐太郎、俺ぁいっぺんお前に訊きたいと思っているんだが、
今の若い噺家さんはネ、落とし噺のおかしみの所だけ演ったり、ステテコの真似をして踊ったりすると人気も出るし、お席亭も喜ぶ。お前ェもやる気は無ェか?」
「冗談言っちゃァいけませんよ師匠。あっしゃこの怪談噺でもって生涯ェ、通しますよ。エェ。世の中に、怪談を演る奴があっし一人になったって演りまさぁ」
「・・・偉い。ウン、一筋道てンだな。
アハハ。そうか。じゃ演ってくれよ」
西柳師匠も佐太郎も、怪談噺に誇りを持っている点では共通しています。
しかし時代の流れに抗わず、消えるならばアッサリと消えていこうとする西柳師匠の達観と、あくまで怪談噺を守り通すのだという、若い佐太郎の情熱。この対比がまた味わい深いです。
又ここには、正蔵師匠自身の姿も否応なく重なってきます。
爆笑王:林家三平師匠などが人気を博す世論のなかで、孤独に怪談噺を貫いたのが正蔵師匠でした。
しかしその教え子からは、怪談噺を継承する噺家は現れませんでした。
晩年の正蔵師匠の胸中は、西柳師匠と佐太郎、どちらに近いものだったのでしょうか。
まとめ
林家正蔵師匠は
- 空気感がスゴい
- 笑えないところがスゴい
- スローさがスゴい
まずは「やんま九次」「生きている小平次」「二つ面」からどうぞ。